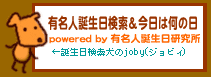年長か年少か
日本では4月1日と4月2日が境目
日本では、1月1日から4月1日までに生まれた人は「早生まれ」、4月2日から12月31日までに生まれた人は「遅生まれ」と呼ばれます。最大で1年近くの発達の差が生まれるわけですね。同学年として長い人生を歩むわけですが、果たしてどちらが得なんでしょうか。
スポーツの世界では、「遅生まれが有利」という現象が長い間注目されてきました。例えば、プロサッカーやアイスホッケーの選手では、学年の初めの月に生まれた選手(遅生まれ)が多いという統計があります。これは「相対年齢効果」と呼ばれる現象で、同じ学年内でも身体的・精神的に成熟した早生まれの子どもが、スポーツの選抜で有利になる傾向を示しています。
相対的年齢効果(Relative Age Effect, RAE)
カナダで行われた調査では、アイスホッケーのジュニアリーグ選手のうち、学年初め(1~3月生まれ)の選手が40%を超えていたのに対し、学年末(10~12月生まれ)の選手はわずか10%台だったという結果が得られました。(カナダのジュニアホッケーでは、1月1日~12月31日で学年・カテゴリが区切られています。)
このように、遅生まれの優位性がスポーツで顕著に現れる傾向があります。もちろん早生まれにも成功する例がないわけではありませんが、統計的には不利であることは間違いありません。この傾向はとくに幼少期に強く、学力テストの成績においても、低学年では早生まれの方が不利になりやすいと言われています。
しかしながら、人生はスポーツや学校のテストばかりじゃありません。
スポーツ以外も含めた人生全体で考えたとき、早生まれと遅生まれのどちらが「得」と言えるのでしょうか? ここでは、学業や社会での経験をもとに、両者の特性を詳しく検証していきます。
遅生まれ(4月~12月生まれ)の強みと弱み
「遅生まれ」の強み
- 幼少期の優位性
遅生まれは同学年内で身体的・精神的に成熟しているため、幼少期からリーダーシップを発揮しやすい傾向があります。とくに幼稚園や小学校低学年などの初期の教育段階では、数か月の差が大きな影響を与えるため、学業成績やスポーツで頭角を現すケースが多く見られます。 - 初期の評価で得られるチャンス
幼い頃の成功体験が自己肯定感を高め、周囲からの期待も後押しするため、その後のキャリアにもプラスに働くことがあります。
「遅生まれ」の弱み
- プレッシャーの増加
幼少期に優れた成績を残すことで、遅生まれの子は常に期待される立場に置かれがち。子どもの性格によってはそのプレッシャーがストレスとして作用する場合があります。 - 相対的な伸びしろの減少
年齢が上がるにつれて、他の同級生が追いついてくるため、相対的な優位性が薄れてしまうことがあります。とくに成長期後半では、身体的な差がなくなることが多いです。
早生まれ(1月~3月生まれ)の強みと弱み
「早生まれ」の強み
- 逆境からの成長
早生まれは遅生まれに比べて幼少期に不利な立場に置かれることが多いです。しかし、それがきっかけとなり努力や忍耐力が養われやすいとも言えます。長期的にみたとき、この「鍛えられた力」が、大きな成功につながることも珍しくありません。 - 後半での巻き返し
高校生や大学生になる頃には、身体的・精神的な成熟度で遅生まれとの差がほとんどなくなるため、追いつき追い越す例も多く見られます。
「早生まれ」の弱み
- 幼少期の不利
小さい頃の身体的・精神的な未熟さから、学業やスポーツで選抜されにくい傾向があります。これが自己肯定感の低下につながる場合もあります。 - 遅れを取り戻すのは大変
努力を重ねても、初期に得られるチャンスが少ないため、遅生まれの同級生に追いつくまで時間がかかることがあります。
結論~学術的な観点からのまとめ
学術研究によると、早生まれと遅生まれのどちらが「得」かは、一概に決められるものではありません。短期的には遅生まれが有利とされますが、早生まれにも、長期的にみれば追いつく、あるいは追い越すチャンスが豊富に存在します。大切なのは、早生まれや遅生まれにかかわらず、与えられた環境でどのように努力し、成長していくかです。
遅生まれは短期的な成功に強みを持ち、早生まれは逆境を乗り越えて長期的に成果を出す可能性があります。どちらが「得」かは、環境や個人の努力次第と言えるでしょう。このコラムを読んだ皆さんも、ぜひ自分や身近な人の「生まれ月」による特徴を見つめ直し、長所を活かして成長するヒントにしてください!